月から始まる各国の太陽系探査
太陽系の惑星配列は、一番内側から水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星と位置しています。
太陽の半径は約69万6000km、地球の半径は約6380kmです。
太陽と地球の距離は約1億4960万km、地球は適切な距離に位置して液体状態の水を持つことができ、生命体の生存できる惑星です。
各国の主な太陽系探査の年譜と略詳細は、次のようになります。
月(半径約1,740km)
地球からの距離は35万6400〜40万6700km
・1959年:旧ソ連「ルナ2号」が月面到達、「ルナ3号」が初めて月の裏側を撮影。
・1969年:米国「アポロ11号」で初の月面着陸成功、2人の宇宙飛行士ニール・アームストロングとエドウィン・オルドリンが初めて月面を歩きました。
・2007年:日本「かぐや」が周回軌道に入り、精密な全球地図を作製。
・2008年:インド「チャンドラヤーン」が周回軌道に入る。
・2013年:中国「ジョウガ3号」が軟着陸し探査車を降ろす。
水星(半径約2,440km)
地球からの距離は8210万〜2億1710万km
・1974年~75年:米国「マリナー10号が3度の接近観測をし、磁場と磁気圏活動があることが発見されました。
・2011年:米国「メッセンジャー」が周回軌道にはいる。
・2017年:日本・欧州宇宙機関(ESA)共同で「ベピ・コロンボ」打ち上げ予定。
金星(半径約6,050km)
地球からの距離は3950万〜2億5970万km
・1962年:米国「マリーナ2号」が初の接近観測に成功する。
・1970年:旧ソ連「ベネラ7号」が初の着陸に成功する。
・2015年:日本「あかつき」が周回軌道に入る。
金星を9日間程度で周回する楕円軌道へと移行し、2016年4月頃から本格的な観測予定です。
火星(半径約3,400km)
地球からの距離は5580万〜4億40万km
・1971年:旧ソ連「マルス3号」が着陸機を降下させる。
・1976年:米国「バイキング1、2号」が相次いで軟着陸する。
・2004年:米国 探査車「スピリット「オポチュニティー」着陸する。
・2012年:米国 探査車「キュウリオシティー」着陸して、過去に大量の水があったことや、塩分の存在が明らかになる。
・2014年:インド「マンガルヤーン」が周回軌道に入る。
木星(半径約71,500km)
地球からの距離は5億9070万〜9億6580万km
・1973年~74年:米国「パイオニア10、11号」が相次いで接近観測する。
・1979年:「ボイジャー1、2号」が相次いで接近観測、衛星イオの火山活動を発見する。
・1995年:「ガリレオ」が周回軌道に入る。
彗星の木星衝突などを観測し、衛星エウロパの地下の海を発見する。
土星(半径約60,300km)
地球からの距離は12億130万〜16億5310万km
・1979年:米国「パイオニア11号」が接近観測する。
・1980年~81年:米国「ボイジャー1、2号」が相次いで接近観測する。
衛星タイタンの大気を発見する。
・2004年:米国「カッシーニ」が周回軌道に入る。
衛星エンセラダスの地下に海があり間欠泉のように噴出すことを発見する。
土星の衛星タイタン(半径約2,580km)
・2005年:欧州宇宙機関(ESA)着陸機「ホイヘンス」が着陸する。
天王星(半径約25,600km)
地球からの距離は25億8650万〜31億5550万km
・1986年:米国「ボイジャー2号」が接近観測し、新たな衛星や輪を発見する。
海王星(半径約24,800km)
地球からの距離は43億1050万〜46億8610万km
・1989年:米国「ボイジャー2号」が接近観測し、新たな衛星や衛星トリトンの火山活動を発見する。
冥王星(半径約1,190km)
地球からの距離は42億9150万〜72億2350万km
・2015年:米国「ニューホライズンズ」が接近観測し、地下活動をうかがわせる山や氷河を発見する。
小惑星
・2005年:日本「はやぶさ」が小惑星イトカワに着陸し試料採取、2010年に地球に帰還しました。
イトカワは、大きさ 535×294×209m、地球からの距離は178万〜4億500万kmです。
・2011年:米国「ドーン」が小惑星ベスタの周回軌道に入る。
・2018年:日本「はやぶさ2」が小惑星1999JU3に到着する予定です。
彗星
地球からの距離は27億km 尾の長さは最大で1億2000万km
・1986年:旧ソ連「ベガ1、2号」がハレー彗星に接近観測し、500枚以上の画像を撮影し、核の大きさや温度、彗星のガス雲(塵)の組成などを解明しました。
・1986年:欧州宇宙機関(ESA)「ジオット」がハレー彗星に接近観測し、その核が雪玉状の組成で、ひょうたん型の形をしていることを明らかにしました。
・1986年:日本「さきがけ」「すいせい」がハレー彗星に接近観測し、彗星付近の太陽風磁場やプラズマを観測しました。
・2004年:米国「スターダスト」がビルト2彗星に接近、彗星からの物質を採取する。
・2014年:欧州宇宙機関(ESA)「ロゼッタ」がチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に接近、着陸機を降ろす。
2016年9月以降は、彗星が太陽から離れてしまうため、太陽電池で十分な電力が得られず、観測が続けられなくなります。
その前に、「ロゼッタ」本体を彗星表面に着陸させるという計画も発表されました。
More from my site
関連記事
-

-
失敗!カクテルの飲みすぎは要注意
酒は飲んでも飲まれるな、とはよく言いますが、ついつい飲みすぎて失敗してしまった… …
-

-
南極の氷は減ってるの?増えてるの?
南極大陸は1億6000万年前にアフリカ大陸と分離。 4000万年前にはオーストラ …
-

-
ビール缶を1/4につぶす方法
ビールの飲んだ後のカンはゴミとしてリサイクルに出すにしても、非常にかさばります。 …
-

-
東京タワーのフットタウン屋上から天体観測
東京タワーフットタウンは、東京タワーの中心足下にある地下1階と地上5階建て多目的 …
-

-
突然の生理痛 事前に漢方服用で緩和
女性であれば、ほとんどの場合毎月やってくる生理。 痛みや不快感を伴う方も多くいら …
-

-
東京ドームを一円玉の大きさにしてみたら10m先に富士山が見えた!
東京ドーム周辺 床に落ちていた一円玉を座って上から見ると、白い屋根の東京ドームに …
-

-
素人講師たちによるソバ打ち体験教室に参加したけれど・・・お粗末でした
昨年の秋に、私の住んでいる市が企画したソバ打ち体験教室に参加しました。 この催し …
-

-
朝のランニング
今日もAM5時半、家を出て1キロ程先にある公園へ向かいランニングです。 週4,5 …
-
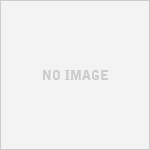
-
紅茶をおいしく飲む秘訣とは?
日本人はコーヒー党が多く、紅茶の飲み方を知らない方が多いと聞きます。 日本では紅 …
-

-
お酒の失敗 後悔は先に立たず
お酒を飲んだ昨夜の出来事を思い出すと、自分の「やっちまった」ことの後悔と体からに …
- PREV
- 日本のエレベーター技術は世界一・世界中で活用
- NEXT
- 瞬間接着剤のかしこい選び方 使い方




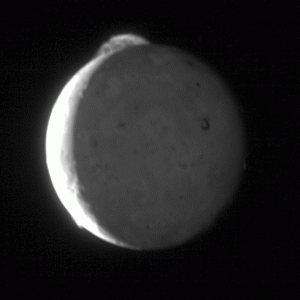








Comment
You are my inhalation, I have few web logs and rarely run out from post eacedeeeddkkgdgb