日本の五節句 / 七草・桃の節句・端午の節句・七夕・重陽の節句
2025/12/15
江戸時代に幕府が公的な行事・祝日として、人日の節句、上巳の節句、端午の節句、七夕の節句、重陽の節句の五節句を定めました。
節句は、日本の暦の一つであり、伝統的な年中行事を行う季節の節目となり、子供から大人まで一般に広く定着しています。
● 七草の節句=人日(じんじつ) 1月7日
和名で七草の節句といい、一年の無病息災を願って、七草粥を食べられる風習です。
祝膳や祝酒で弱った胃を休める為とも言われています。
中国からつたわり、日本では平安時代から始められ、江戸時代より一般に定着しました。
また、新年になって初めて爪を切る日、爪切りの日にもなっています。
七草を浸した水に爪をつけ、柔かくして切ると、その年は風邪をひかないと言われています。
● 雛祭り=上巳(じょうし) 3月3日
雛祭り(ひなまつり)は、ひいなあそびともいい、女子のすこやかな成長を祈る節句の年中行事です。
七草の節句ともいい、男雛と女雛を中心とした「ひな人形」を飾り、雛あられや菱餅を供えて、桃の花を飾り、白酒や寿司などの飲食を楽しむ節句祭りです。
雛祭りは、いつ頃から始まったのか歴史的には判然としません。
平安時代の京都で既に平安貴族の子女の雅びな「遊びごと」として行われていた記録が現存していますが、江戸時代になり女子の「人形遊び」と節物の「節句の儀式」と結びつき、全国に広まり、飾られるようになったようです。
● 端午(たんご)の節句 5月5日
鎌倉時代ごろから菖蒲(しょうぶ)の葉の形が剣を連想させることなどから、端午は男の子の節句とされ、男の子の成長を祝い健康を祈るようになりました。
鎧、兜、刀、武者人形や金太郎・武蔵坊弁慶を模した五月人形などを室内の飾り段に飾り、庭前にこいのぼりを立てるのが、典型的な祝い方です。
端午の日にはちまきや柏餅(かしわもち)を食べる風習もあります。
● 七夕(しちせき) 7月7日
そもそも七夕とはお盆行事の一環でもあり、精霊棚とその幡を安置するのが7日の夕方であることから7日の夕で「七夕」と書いて「たなばた」と発音するようになったともいわれます。
二星会合(織女と牽牛が合うこと)や詩歌・裁縫・染織などの技芸上達が願われ、江戸時代には手習い事の願掛けとして一般庶民にも広がりました。
笹の節句ともいい、全国的には、短冊に願い事を書き葉竹に飾ることが一般的に行われています。
また、仙台などでは、麺を糸に見立て、織姫のように機織・裁縫が上手くなることを願うという説から、裁縫の上達を願いそうめんが食べられたりします。
日本の七夕祭りは、新暦7月7日や月遅れの8月7日、あるいはそれらの前後の時期に開催されています。
● 重陽(ちょうよう)の節句 9月9日
陽の数である奇数の極である9が2つ重なることから重陽と呼ばれ、たいへんめでたい日とされています。
菊の節句ともいい、邪気を払い長寿を願って、菊の花を飾ったり、菊の花びらを浮かべた酒を酌み交わして祝ったりします。
現在では、他の節句と比べてあまり実施されていないようです。
More from my site
関連記事
-

-
彼氏・彼女へのクリスマスプレゼント / ベスト10
全国平均で、女性から男性に贈るクリスマスプレゼントの予算平均額はおおよそ11,0 …
-

-
真夏の遮熱性舗装と生活道路とマラソンコース
辞書では遮熱(しゃねつ)とは放射熱を遮蔽することをいう。 では遮蔽(しゃへい)っ …
-

-
家庭菜園をするための「心構えと注意ポイント」
まず家庭菜園で作るなら、何を作るのか考えないといけませんね。 野菜によっては簡単 …
-

-
ミノムシの糸は自然界最強の繊維だった
小枝にぶら下がっているミノムシは、ミノガの幼虫が糸を吐いて蓑状(ミ …
-
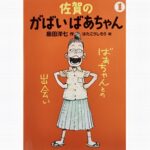
-
佐賀県の武雄市 地味でもそこには日本の原風景が!
地味であまり知られていない佐賀県ですが、福岡県と長崎県そして玄界灘と有明海に挟ま …
-

-
ニラ/ミニトマト/スイカを家庭菜園で作ってみました
一軒家を持つ事が出来て庭に小さな花壇を作りました。 花を育てるのに慣れてきた頃、 …
-

-
細分化で掃除の負担を少なくする
毎日忙しく時間に追われた生活をしていると、家事の中でも一番後回しになりがちなのが …
-

-
初めてパッションフルーツを作ってみました!
パッションフルーツを育てた経験について紹介したいと思います。 パッションフルーツ …
-

-
冷房効果を早くする方法
朝の出勤や外出先などから帰宅すると部屋中が異常に暑くなっていることがよくあると思 …
-

-
本州最北端のマグロの街は遠くも食に大満足!
昨年の秋、夫婦で東北地方、主に北東北をめぐってきました。 岩手県から向かった先は …










