現在使える貨幣の種類と詳細です
2026/01/09
 現在日本で発行されている貨幣(通常貨幣)は、1円、5円、10円、50円、100円、500円の各1種類ずつで6種類と、臨時発行の記念貨幣があります。
現在日本で発行されている貨幣(通常貨幣)は、1円、5円、10円、50円、100円、500円の各1種類ずつで6種類と、臨時発行の記念貨幣があります。
現在、市中で流通しているのは
◍ 一円アルミニウム貨
◍ 五円黄銅貨(孔あり文字ゴシック体)
◍ 十円青銅貨(ギザ無)
◍ 五十円白銅貨
◍ 百円白銅貨
◍ 五百円ニッケル黄銅貨など。
◍ 五百円バイカラー・クラッド貨
既に発行を終了したものは
◍ 五円黄銅貨(孔あり文字楷書体)
◍ 十円青銅貨(ギザあり)
◍ 五百円白銅貨
これらは自動販売機等で受け付けられないこともあります。
その他には、
◍ 五円黄銅貨(孔なし)
◍ 五十円ニッケル貨(孔なし)
◍ 五十円ニッケル貨(孔あり)
◍ 百円銀貨(鳳凰)
◍ 百円銀貨(稲穂)
などありますがほとんど流通はないようです。
でも現在でも使える硬貨です。
「1円玉」
新1円硬貨 製造発行中

1955年(昭30)に発行され流通が始まりました。
デザインは一般公募で決まり、アルミニウムの「1円玉」は硬貨の中で最も軽い1gで直径20mmです。
表面に「葉が8枚の若木(わかぎ)」が描かれ、「日本国」と「一円」が記されています。
「若木」は特定の植物を指してはいません。
裏面は数字の「1」と製造年が記されています。
一円硬貨の比重は2.7で水より重いが、乾いた一円硬貨を水面に対して平らになるように静かに置くと、一円硬貨にかかる浮力と表面張力が一円硬貨の重量と釣り合うため水に浮きます。
「5円玉」
初代の5円硬貨(孔なし)

製造発行は1948年(昭23)~1949年(昭24)
黄銅貨、直径22mm、重さ4.0g、周囲にギザあり
※黄銅は銅と亜鉛の合金
表面に「国会議事堂」と「五円」の文字、周囲を「唐草模様」が取り囲むデザインです。
裏面には「鳩と梅花」、「日本國」と製造年が記されています。
2代目の5円硬貨(孔あり)
 製造発行は1949年(昭24)~1958年(昭33)
製造発行は1949年(昭24)~1958年(昭33)
黄銅貨、直径22mm、重さ3.75g、孔径5mm、周囲にギザなし
表面に農業・水産業・工業を表す「稲穂・水・歯車」が描かれ「五円」の楷書体文字が記されています。
裏面は穴の左右に、成長と民主主義を表す「双葉」が描かれ、上に「日本國」と下に製造年が楷書体文字で記されています。
3代目の5円硬貨(孔あり)製造発行中

製造発行は1959年(昭34)~現在
黄銅貨、直径22mm、重さ3.75g、孔径5mm、周囲にギザなし
表面に農業・水産業・工業を表す「稲穂・水・歯車」が描かれ、「五円」のゴシック体文字が記されています。
裏面は穴の左右に、成長と民主主義を表す「双葉」が描かれ、上に「日本国」と下に製造年がゴシック体文字で記されています。
「10円玉」
初代の10円硬貨

製造は1951年(昭26)から、発行は1953年(昭28)~1958年(昭33)
青銅貨、直径23.5mm、重さ4.5g、周囲縁にギザがあり「ギザ十」と呼ばれています。
表面に世界遺産「平等院鳳凰堂」、「日本国」と「十円」の文字が記され、周囲には唐草模様が描かれています。
裏面は「10」と製造年、その周りをリボンで結ばれた「常盤木」が描かれています。
常盤木は松の別名で縁起のよい木とされました。
偽装対策としての「平等院鳳凰堂」の緻密な表現が凄いです。
2代目の10円硬貨 製造発行中

製造発行は1959年(昭34)~現在
青銅貨、直径23.5mm、重さ4.5g、周囲にギザなし
表面、裏面のデザインは初代10円硬貨とまったく同じです。
「50円玉」
初代の50円硬貨(孔なし)

製造発行は1955年(昭30)~1958年(昭33)
純ニッケル貨で、直径25mm、重さ5.5g、周囲にギザあり
表面中央に「菊花」、上に「日本国」下に「五十円」の文字が記されています。
裏面中央には「分銅」とアラビア数字の「50」、上に「昭和」と下に製造年の文字が記されています。
ニッケル貨は磁石に付く特性を持ち、自販機や鉄道駅の券売機、ATM、自動釣銭機等の機器で受け付けられないなど故障を起こす可能性もありました。
2代目の50円硬貨(孔あり)

製造発行は1959年(昭34)~1966年(昭41)
純ニッケル貨で、直径25mm、重さ5.0g、孔径6mm、周囲にギザなし
表面中央に真上から見た1輪の「菊」、上に「日本国」下に「五十円」の文字が記されています。
裏面には上に「50」、下に製造年の文字が記されています。
ニッケル貨は磁石に付く特性を持ち、初代50円硬貨と同様に自販機や鉄道駅の券売機、ATM、自動釣銭機等の機器で受け付けられないなど故障を起こす可能性もありました。
3代目の50円硬貨 製造発行中
 製造発行は1967年(昭42)~現在
製造発行は1967年(昭42)~現在
白銅貨で、直径21mm、重さ4.0g、孔径4mm、周囲に120本のギザあり
表面は穴の左右に三輪の「菊の花」が、孔の上に「日本国」下に「五十円」の文字が記されています。
裏面には上にアラビア数字で「50」、下に製造年が刻まれています。
孔とギザとを同時に有する硬貨は3代目50円硬貨のみ。
「100円玉」
製造発行は1957年(昭32)~1958年(昭33)
銀貨(銀60%,銅30%,亜鉛10%)で、直径22.6mm、重さ4.8g、周囲にギザあり
表面中央には「鳳凰」、上に「日本国」下に「百円」の文字が記されています。
裏面中央に「旭日・桜花」、その周りを「100」「YEN」「昭和」と製造年の文字が囲む様に記されています。
百円銀貨の品位は、2025年(令7)時点での銀相場が、1グラムあたり280円前後で推移していますので、百円銀貨に含まれる銀の価格は280×4.8×0.6=806円となり額面金額を大きく超えます。
2代目の100円硬貨(稲穂)

製造発行は1959年(昭34)~1966年(昭41)
銀貨(銀60%,銅30%,亜鉛10%)で、直径22.6mm、重さ4.8g、周囲にギザあり
表面中央には「稲穂」、上に「日本国」下に「百円」の文字が記されています。
裏面には分銅と中央に「100」、上に「昭和」と下に製造年の文字が記されています。
百円銀貨の品位は、鳳凰百円銀貨と同じ806円となり額面金額を大きく超えます。
3代目の100円硬貨 製造発行中
 製造発行は1967年(昭42)~現在
製造発行は1967年(昭42)~現在
白銅貨、直径22.6mm、重さ4.8g、周囲に103本のギザあり
表面中央には日本の国花でもある三輪の「山桜」、上に「日本国」下に「百円」の文字が記されています。
裏面にはアラビア数字で「100」、下に製造年が記されています。
直径、量さは前発行されていた2種類の百円銀貨と同じです。
自販機など普段の生活で一番使用する硬貨です。
「500円玉」
初代の500硬貨
 製造発行は1982年(昭57)~1999年(平11年)
製造発行は1982年(昭57)~1999年(平11年)
白銅貨、直径26.5mm、重さ7.2g、厚み1.85 mm、周囲縁には NIPPON ◆ 500 ◆の刻レタリングあり
表面中央には桐の花葉、上に「日本国」下に「五百円」の文字が記されています。
裏面中央には「500」その下に製造年が記され、上下に竹の葉、左右に橘の小枝がデザインされています。
2代目の500硬貨



製造発行は2000年(平12年)~2021年(令3年)
ニッケル黄銅貨、直径26.5mm、重さ7.0g、厚み1.81mm、周囲に181本の斜めギザあり
表面中央には桐の花葉、上に「日本国」下に「五百円」の文字が記されています。
裏面中央には「500」その下に製造年が記され、上下に竹の葉、左右に橘の小枝がデザインされています。
裏面を上に傾けると「500」の”0”の部分に縦線が浮かび、下に傾けると「500円」の文字が浮かび上がります。
表面、裏面のデザインなど大まかな外観に初代白銅貨との差はありませんが、偽造防止などのために潜像やマイクロ文字などデザインが変更されています。、
造幣局は公表していないそうですが、肉眼では分からない「NIPPON」という6文字の0.2mmのマイクロ文字が表裏両面に刻印されています。
3代目の500硬貨 製造発行中




製造発行は2021年(令3年)~現在
バイカラー・クラッド貨(外縁部分:ニッケル黄銅、表面と裏面の中心部分:白銅、表面と裏面に挟まれた中心部分:銅)
直径26.5mm、重さ7.1g、厚み1.81mm、周囲に異形斜めギザあり
表面中央には桐の花葉、上に「日本国」下に「五百円」の文字が記されています。
表面縁には「JAPAN」と「500YEN」が映る微細文字が加工。
裏面中央には「500」その下に製造年が記され、上下に竹の葉、左右に橘の小枝がデザインされています。
裏面を上から見ると「500」の”0”の部分に「JAPAN」が浮かび、下から見ると「500YEN」の文字が浮かび上がります。
表面、裏面のデザインなど大まかな外観に初代白銅貨との差はありませんが、2代目同様、偽造防止などのために潜像やマイクロ文字などデザインが変更されています。
◇ ◇
一円硬貨1枚を製造するのにかかるコストは額面以上で、2015年(平成27年)現在、約3円かかるとされます。
五円硬貨や十円硬貨も同様に、硬貨に使われる素材の金属価値は額面より低いですが、製造コストは額面以上となっています。
貨幣の製造原価(推計による)
硬貨 製造コスト
◍ 1円玉 約3.1円
◍ 5円玉 約10.1円
◍ 10円玉 約12.9円
◍ 50円玉 約12.1円
◍ 100円玉 約14.6円
◍ 500円玉 約19.9円
貨幣製造コストの内訳
製造原価の3つの要素として
◍ 原材料費: 金属相場の変動と影響
◍ 加工費: 製造工程の複雑さによって変動
◍高度な偽造防止技術に関わる費用
ちなみに、紙幣の製造コストは、日本銀行が国立印刷局から買い上げる価格で、お札1枚あたりのコストは、推計約22~24円とされています。
More from my site
関連記事
-

-
洗濯物は工夫して干します
洗濯物は繊維別に干しましょう 化繊ものと天然繊維ものとに区別して、 …
-
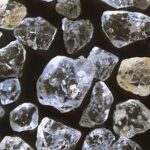
-
鳴り砂 鳴き砂のメカニズム
海岸で乾いた砂の上を歩くと、キユ、キュ、キュ、キュと足元で可愛い音がすることがあ …
-

-
衣類は繊維別にしまい傷みから避けましょう
衣類は、ほこりや直射日光を避けるためにタンスなどにしまいますが、湿気にも気を付け …
-

-
ネットでの下着の買い物では失敗続き
最近、下着の買い物では失敗続きかもしれません。 それは下着といっても補正下着なの …
-

-
広島生まれが紹介する広島の定番と豆知識
広島県で生まれ、大学で上京するまで18年間広島県に住んでいました。 そこで、地元 …
-
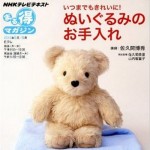
-
汚れてしまったぬいぐるみを綺麗にしてみましょう
かわいいぬいぐるみは、幼児のオモチャとはかぎりません。 ちかごろでは、子供のいな …
-

-
玉露とほうじ茶のおいしい入れ方
玉露や緑茶をおいしく入れるポイントは、茶葉に含まれる旨み成分(テアニンなど)を引 …
-

-
寝る子は育つ!と言うけれど寝る大人は育つの?
「寝る子は育つ!」よく聞くことばですね。 赤ちゃんは毎日16時間も眠っています。 …
-

-
函館氷は夏の必需品のはじまりでした
氷には河川や湖水の冬季に氷結した物を切り出して保存・利用する「天然氷」と、機械に …
-

-
日本の五節句 / 七草・桃の節句・端午の節句・七夕・重陽の節句
江戸時代に幕府が公的な行事・祝日として、人日の節句、上巳の節句、端午の節句、七夕 …







